有機農業の市場はアジアでも拡大している。日本は遅れを取るのか
2021年10月28日
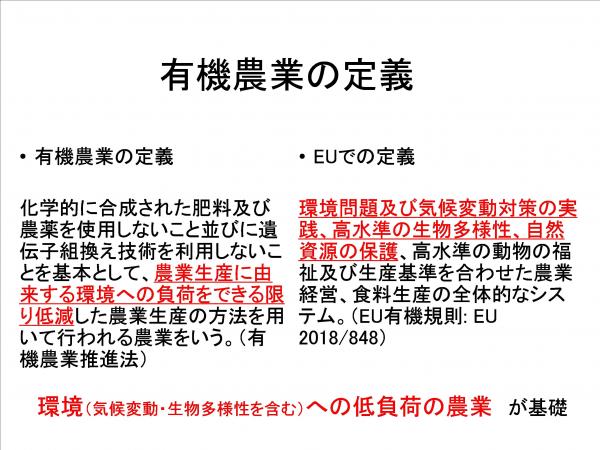
輸出入品であっても、整合性があり、基準を満たしていれば認められることもある。従って有機と謳(うた)っている産品が国産とは限らない。例えば、大豆を使った食品や飲料などの有機産品の原材料をみると、必ずしも国産ではないこともある。既にグローバルなサプライチェーンに関係していることに気づかされる。
 900年の歴史があるマリア・ラーハ修道院近くのオーガニックショップに並ぶ有機野菜=2019年11月、ドイツ・ラインラント=プファルツ州、筆者撮影
900年の歴史があるマリア・ラーハ修道院近くのオーガニックショップに並ぶ有機野菜=2019年11月、ドイツ・ラインラント=プファルツ州、筆者撮影日本は、欧州とは所得補償などで異なるアプローチを取るものの、規模、環境面での配慮、域内(日本の場合は国内)産品の抱える事情は、米国、豪州、南米の国々との比較よりは意義があり、実際に欧州の分析は活発に行われてきた。
欧州との比較が盛んになりがちなのは、環境条約における米国の姿勢が関係している。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください